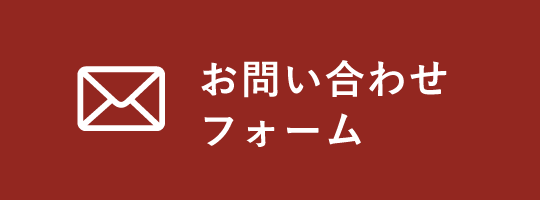Posts Tagged ‘逮捕後の流れと対処法’
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違いは?それぞれのメリット・デメリット
はじめに
突然、家族が逮捕された。あるいは、警察から在宅事件の捜査で呼び出しを受けた。このようなとき、多くの方が「弁護士に相談しなければ」と考えるでしょう。しかし、刑事事件に関わる弁護士には、「当番弁護士」「国選弁護人」「私選弁護人」という3つの種類があり、それぞれに大きな違いがあることをご存じでしょうか。
どの弁護士に依頼するかは、依頼できるタイミング、費用、そして何より弁護活動の質に直結し、事件の最終的な結果を大きく左右する重要な選択です。
この記事では、これら3種類の弁護士の違いを、メリット・デメリットと共に徹底的に比較し、あなたがどの弁護士を選ぶべきかを判断するための材料を、弁護士法人長瀬総合法律事務所が提供します。
Q&A
Q1. とりあえず無料で来てもらえる当番弁護士に依頼すれば十分ですか?
当番弁護士は、逮捕された方が初回に限り、無料で弁護士を呼べるという、非常に重要な制度です。逮捕直後の不安な状況で、取り調べへの対応など緊急のアドバイスを受けられるメリットは大きいです。しかし、当番弁護士の役割は、あくまで1回限りの接見が原則です。被害者との示談交渉や、勾留を防ぐための意見書の作成といった継続的な弁護活動は、別途、私選弁護人として依頼し直さない限り、行ってもらえません。緊急の応急処置としては有効ですが、それだけで事件を最後まで乗り切るのは困難です。
Q2. 国選弁護人は、やる気がないと聞きますが本当ですか?
「国選弁護人はやる気がない」というのは、必ずしも正しくありません。国から選任された責任感から、熱心に活動する弁護士も数多くいます。しかし、問題は弁護士を自分で選べないという点にあります。そのため、残念ながら刑事事件の経験が少ない弁護士や、相性の悪い弁護士が担当になる可能性も否定できません。また、報酬が比較的低額であることや、解任が原則できない制度であることから、結果として活動が低調に見えてしまうケースがあるかもしれません。
Q3. 弁護士費用が高い私選弁護人を選ぶ、一番のメリットは何ですか?
私選弁護人を選ぶ最大のメリットは、活動開始のタイミングとスピードです。国選弁護人は勾留された後でなければ選任されませんが、私選弁護人であれば、逮捕直後の最も重要な72時間、あるいは事件化する前の段階から、迅速に活動を開始できます。勾留を阻止したり、早期に示談を成立させて不起訴処分を目指したりと、有利な結果を導くための初動対応ができるのは、私選弁護人ならではの強みです。費用はかかりますが、それに見合うオーダーメイドの弁護活動が期待できます。
解説
3種類の弁護士の違いを、項目ごとに詳しく見ていきましょう。
1. 当番弁護士 – 逮捕直後の「初回無料相談」
- 制度の概要
弁護士会が運営しており、逮捕された方が警察官などを通じて依頼すると、1回に限り無料で弁護士が接見に来てくれる制度。 - 依頼できる人
逮捕された被疑者(またはその家族など)。 - タイミング
逮捕後、いつでも。 - 費用
初回無料。 - 弁護士の選定
選べない。 弁護士会の名簿に基づき、その日の担当弁護士が派遣される。 - メリット
費用を気にせず、逮捕直後の孤独で不安な状況で、すぐに弁護士に会ってアドバイスをもらえる点です。取り調べに対する心構えなどを聞くだけでも、大きな精神的支えになります。 - デメリット
あくまで1回きりの派遣が原則であり、継続的な活動はしてくれません。被害者との示談交渉や、検察官・裁判官への意見書提出といった本格的な弁護活動を依頼するには、その当番弁護士と改めて私選契約を結ぶか、別の私選弁護人を探す必要があります。
2. 国選弁護人 – 資力がない人のための「国が選ぶ弁護士」
- 制度の概要
経済的な理由で弁護士費用を払えない被疑者・被告人のために、国が費用を負担して選任する弁護士。 - 依頼できる人
勾留された被疑者、または起訴された被告人で、資力基準(預貯金などが50万円以下)を満たす人。 - タイミング
被疑者段階では「勾留された後」、被告人段階では「起訴された後」。 - 費用
原則として国が負担。ただし、裁判後に資力があると判断された場合は、費用の支払いを命じられることがあります。 - 弁護士の選定
選べない。 裁判所が名簿から機械的に選任する。 - メリット
弁護士費用をほとんど気にすることなく、継続的な弁護活動を受けられる点です。 - デメリット
- 活動開始が遅い
最大のデメリットです。勾留が決定された後でないと選任されないため、逮捕から勾留決定までの最も重要な最大72時間の弁護活動ができません。 - 弁護士を選べない
刑事事件の経験や熱意、人柄などは弁護士によって千差万別です。相性が合わなくても、原則として解任や変更はできません。
- 活動開始が遅い
3. 私選弁護人 – 自分で探し、自分で選ぶ「オーダーメイドの弁護人」
- 制度の概要
被疑者・被告人やその家族が、自らの意思で探し、委任契約を結んで依頼する弁護士。 - 依頼できる人
誰でも。 - タイミング
いつでも。 警察から連絡が来た段階、逮捕される前、逮捕直後、在宅事件、起訴後など、どのステージからでも依頼可能。 - 費用
依頼者が全額を負担。費用は法律事務所によって異なります。 - 弁護士の選定
自由に選べる。 複数の事務所に相談し、実績、専門性、費用、そして何より人柄や相性を比較検討して、最も信頼できる弁護士を選べます。 - メリット
- 迅速な初動対応
逮捕直後の72時間、勾留が決まる前の「ゴールデンタイム」に活動を開始し、早期の身柄解放や不起訴処分を目指せること。これが最大の強みです。 - 高い専門性と質の高い弁護活動
「刑事事件に強い」「示談交渉が得意」など、その事件に最適な専門家を選ぶことができ、手厚く質の高い弁護活動が期待できます。 - 依頼者との密な連携
契約に基づいているため、報告・連絡・相談が密になり、依頼者の希望に沿ったオーダーメイドの弁護戦略を立てることができます。
- 迅速な初動対応
- デメリット
弁護士費用が自己負担となる点です。
【3種類の弁護士 違いのまとめ】
| 比較項目 | 当番弁護士 | 国選弁護人 | 私選弁護人 |
| 依頼タイミング | 逮捕直後(1回のみ) | 勾留後・起訴後 | いつでも |
| 活動開始の速さ | 速い(応急処置) | 遅い | 最も速い |
| 弁護士を選べるか | 選べない | 選べない | 自由に選べる |
| 費用負担 | 無料(初回) | 原則、国が負担 | 自己負担 |
| 専門性・相性 | 未知数 | 未知数 | 重視して選べる |
弁護士に相談するメリット(なぜ私選弁護人がベストか)
ここまで見てきたように、経済的な事情が許すのであれば、私選弁護人を選ぶメリットは計り知れません。
刑事事件の弁護活動は、時間との勝負です。特に、逮捕後の72時間は、その後の人生を左右すると言っても過言ではありません。この重要な時期に、国選弁護人はまだ存在すらしていません。勾留を阻止し、早期に職場や家庭に復帰できる可能性を最大限に高めることができるのは、迅速に動ける私選弁護人だけなのです。
また、被害者との示談交渉、保釈請求、裁判での情状弁護など、刑事事件の各ステージには、高度な専門性と経験、そしてノウハウが求められます。「刑事事件に強い」弁護士を自ら選べるというアドバンテージは、事件の最終結果に影響します。
まとめ
当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人。それぞれに役割と特徴がありますが、あなたとあなたの大切な家族の未来を守るために、最善の結果を追求するのであれば、信頼できる私選弁護人を自ら探し、依頼することが、最良の選択肢であると言えます。
費用は確かにかかります。しかし、それは早期の身柄解放、前科の回避、ひいては失われずに済んだ社会的信用や職といった、プライスレスな価値を得るための投資と考えることもできます。
どの弁護士に依頼するかは、あなたの刑事事件の行方を決める最初の、そして最も重要な決断です。それぞれの違いを正しく理解し、後悔のない選択をしてください。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、あなたとご家族に寄り添い、最善の弁護活動を提供することをお約束します。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に
保釈を勝ち取るには?保釈金の相場と申請手続きの流れ
はじめに
検察官に起訴されてしまった後も、多くの場合、身体拘束は「起訴後勾留」として継続されます。裁判が終わるまで、場合によっては数ヶ月から1年以上もの間、留置場や拘置所での不自由な生活を強いられることは、ご本人にとっても、その帰りを待つご家族にとっても、肉体的・精神的に大きな苦痛となります。
この、起訴後の長期にわたる身体拘束から、保証金を納付することを条件に一時的に解放されるための制度が「保釈」です。保釈が認められれば、自宅から裁判所に通い、社会生活を維持しながら、裁判の準備に集中することができます。
この記事では、どうすれば保釈を勝ち取ることができるのか、そのための条件、必要となる「保釈金」の相場、そして具体的な申請手続きの流れについて解説します。
Q&A
Q1. 保釈金は、だいたいどのくらい用意すればよいのでしょうか?
保釈金の額は、事件の性質や被告人の経済力などによって裁判官が個別に決定するため、一概には言えません。しかし、一般的な相場としては150万円から300万円程度になるケースが多いです。例えば、窃盗や傷害などの一般的な事件であればこの範囲に収まることが多いですが、否認事件や大規模な経済事件などでは、これより高額になる傾向があります。弁護士に依頼すれば、事件の内容からおおよその相場を予測することが可能です。
Q2. 支払った保釈金は、裁判が終わったら返ってくるのですか?
はい、返ってきます。 ここは非常に重要なポイントですが、保釈金は国に納める罰金とは全く性質が異なります。あくまで、被告人が裁判から逃げたり、証拠隠滅をしたりしないことを約束させるための「担保金(人質のようなもの)」です。そのため、保釈中に定められた条件(裁判所からの呼び出しに応じる、関係者に接触しない等)を守り、裁判が終了すれば、判決内容が実刑であったとしても、全額が返還されます。
Q3. どんな事件でも保釈は認められるのですか?
残念ながら、どんな事件でも認められるわけではありません。法律には、保釈を原則として許可しなければならない「権利保釈」が定められていますが、そこにはいくつかの除外事由があります。例えば、過去に重い罪で有罪判決を受けたことがある場合や、常習性がある場合などです。実務上、検察官が最も強く反対してくる理由は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」というものです。否認事件や共犯者がいる事件では、この点を理由に保釈が認められにくくなる傾向があります。しかし、そのような場合でも、弁護士の活動によって保釈が許可される可能性はあります。
解説
起訴後の生活を大きく左右する「保釈」。その制度を詳しく理解し、実現への道をさぐりましょう。
1. 保釈とは?- 起訴後の被告人のための解放制度
保釈とは、起訴された後、勾留されている被告人について、一定の保証金(保釈金)の納付を条件として、その身体拘束を解く制度です。
ここで絶対に押さえておくべき重要なポイントは、保釈は「起訴された後」の被告人のみが利用できる制度であるという点です。起訴される前の「被疑者」の段階では、残念ながら保釈を請求することはできません。
保釈には、法律上、大きく分けて以下の3つの種類があります。
- 権利保釈(必要的保釈)
後述する法律上の除外事由に当てはまらない限り、裁判所が原則として許可しなければならない保釈です。弁護人は、まずこの権利保釈を主張します。 - 裁量保釈
権利保釈の除外事由に該当してしまった場合でも、裁判官が「保釈を許可することが適当である」と裁量で判断した場合に認められる保釈です。被告人の健康状態や、身体拘束が長引くことによる社会的・経済的な不利益の大きさなどを考慮して判断されます。 - 義務的保釈
不当に勾留が長引いた場合に、法律上、裁判所が保釈を許可しなければならなくなる制度ですが、適用されるケースはまれです。
2. 保釈が認められるための「壁」と、それを乗り越える方法
保釈請求が認められるためには、検察官が主張する「壁」を乗り越えなければなりません。特に重要なのが、権利保釈の除外事由である「罪証隠滅のおそれ」です。
権利保釈の主な除外事由
- 死刑、無期もしくは短期1年以上の懲役・禁錮にあたる重大犯罪である
- 過去に、死刑、無期もしくは長期10年を超える懲役・禁錮の有罪判決を受けたことがある
- 常習として長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した
- 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
- 被害者やその親族、証人などに対し、身体や財産に害を加えたり、脅迫したりするおそれがある
- 氏名または住居が分からない
検察官は、保釈に反対する際、ほぼ必ず「被告人を釈放すれば、共犯者と口裏合わせをしたり、被害者を脅して証言を変えさせたりする危険がある」として、「罪証隠滅のおそれ」を主張してきます。
この検察官の主張に対し、弁護人は「もはや罪証隠滅のおそれは具体的には存在しない」ことを、説得的に反論していく必要があります。例えば、「共犯者はすでに逮捕・起訴されている」「被害者との示談が成立しており、接触する必要がない」「重要な証拠はすべて検察官が押収済みである」といった事実を具体的に主張します。
3. 保釈金の相場と、万が一払えない場合の対処法
- 保釈金の目的と相場
保釈金は、被告人に「もし逃亡したり、証拠隠滅をしたりすれば、このお金は没収されてしまう」という心理的なプレッシャーを与え、保釈中の遵守事項を守らせるための担保です。
その額は、犯罪の性質や被告人の資産状況などを考慮して、裁判官が「没収されたら困る」と思える額を決定します。一般的には150万円~300万円が相場ですが、あくまでケースバイケースです。 - 保釈金が返還されるタイミング
保釈の条件を守り、裁判が終了すれば、保釈金は指定の口座に全額返還されます。実刑判決を受けて刑務所に収監される場合でも、判決言渡し後に家族などが手続きをすれば返還されます。 - 保釈金が用意できない場合
親族などから借金をして工面するのが一般的ですが、どうしても用意できない場合は、「日本保釈支援協会」や「全国弁護士協同組合連合会」といった、保釈金の立替支援を行っている機関を利用する方法があります。これらの制度を利用するには審査が必要ですが、弁護士がその手続きをサポートします。
4. 保釈を勝ち取るための手続きの流れ
保釈は、以下のステップで進められます。
- 弁護人による保釈請求書の提出
起訴後、弁護人が速やかに裁判所に対して保釈請求書を提出します。この際、身元引受人(通常は家族)が作成した身元引受書や、示談書など、保釈を認めてもらうのに有利な資料を添付します。 - 裁判官による検察官への意見聴取
保釈請求書を受け取った裁判官は、担当の検察官に対し、保釈についての意見を求めます。検察官は通常、「反対」または「厳格な条件を付すべき」という意見を出してきます。 - 裁判官による判断(許可 or 却下)
裁判官は、弁護人の請求書と検察官の意見書を比較検討し、保釈を許可するかどうかを決定します。 - 保釈許可決定と保釈金の納付
裁判官が保釈を許可すると、保釈金の額が伝えられます。弁護人から連絡を受けた家族などが、裁判所の会計課に現金で保釈金を納付します。 - 釈放
保釈金の納付が確認され次第、被告人が勾留されている警察署や拘置所に釈放の連絡が入り、被告人はその日のうちに釈放されます。
弁護士に相談するメリット
保釈の実現可能性は、弁護士の活動にかかっていると言っても過言ではありません。
- 説得力のある保釈請求書の作成
保釈を認めてもらうには、裁判官に対し「罪証隠滅や逃亡のおそれがない」ことを、いかに具体的に、説得力をもって主張できるかが鍵です。弁護士は、これまでの経験と法的な知識に基づき請求書を作成します。 - 検察官の反対意見への的確な反論
検察官がどのような理由で反対してくるかを予測し、それに対する有効な反論をあらかじめ準備しておくことで、保釈の許可率を高めます。 - 迅速な手続きの遂行
起訴されたら即座に請求書を提出するなど、スピーディーに手続きを進めることで、一日も早い身柄解放を目指します。 - 却下決定に対する不服申し立て
万が一、保釈請求が却下されても、諦めません。その決定に対して不服を申し立てる「準抗告」や、事情が変わったとして再度保釈を請求するなど、粘り強く活動を続けます。
まとめ
保釈は、起訴後の長期にわたる身体拘束から解放され、被告人としての防御権を十分に確保し、社会生活へのダメージを最小限に抑えるための、きわめて重要な制度です。
保釈を勝ち取るための最大のポイントは、裁判官に「この人を釈放しても、逃げたり証拠を隠したりする心配はない」と確信させることです。そのためには、専門家である弁護士による、説得力のある主張と迅速な手続きが不可欠となります。
検察官から起訴されたら、それは身体拘束がさらに長期化する危険信号です。すぐに弁護士に相談し、保釈に向けた準備を始めることが、ご本人とご家族の平穏な生活を取り戻すための第一歩です。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に
刑事裁判の流れを徹底解説|第一審から判決までの期間と準備すべきこと
はじめに
検察官から「起訴(公判請求)しました」と告げられた。それは、いよいよ「刑事裁判」という、非日常的な手続きが始まる合図です。
法廷、裁判官、検察官、証言台…。テレビドラマでしか見たことのない世界に、自分が被告人として立つことを想像し、これから何が起こるのか、どう対応すれば良いのか、強い不安を感じるのは当然のことです。裁判はどれくらいの期間がかかるのか、判決はいつ出るのか、何を準備すればいいのか、疑問は尽きないでしょう。
この記事では、日本の刑事裁判(第一審)が、起訴から判決まで、どのような流れで進んでいくのか、その全体像と各ステップで何が行われるのかを解説します。
Q&A
Q1. 起訴されてから、最初の裁判(第一回公判)までは、どのくらい時間がかかりますか?
一般的には、起訴から約1~2ヶ月後に第一回公判が開かれることが多いです。起訴されると、被告人や弁護人のもとに裁判所から「起訴状」が届きます。その後、弁護人が裁判所と日程を調整して、公判期日が決まります。罪を認めている簡単な事件では1ヶ月程度で開かれることもありますが、争点が多い複雑な事件では、準備に時間がかかり2ヶ月以上先になることもあります。
Q2. 裁判は1回で終わるのですか?
事件の内容によって異なります。罪を認めており、争点がない「自白事件」の場合、1回の公判で審理がすべて終わり、その日のうちに結審(審理の終了)し、後日判決が言い渡されるケースが多いです。一方で、無罪を主張したり、事実関係を争ったりする「否認事件」の場合は、複数回の公判が必要になります。証人尋問などが多くなると、公判が月1回程度のペースで何回も開かれ、審理が長期化します。
Q3. 裁判で無罪になる確率はどのくらいですか?
日本の刑事裁判における有罪率は、99.9%以上と言われています。この数字だけを見ると絶望的に感じるかもしれません。しかし、これには理由があります。検察官は、裁判で有罪にできると確信した事件しか起訴しない(嫌疑不十分なら不起訴にする)ため、起訴された時点である程度、有罪の証拠が固まっている事件が多いのです。だからといって、諦める必要はありません。検察官の証拠に不備があれば、それを追及することで、無罪判決を勝ち取ることは可能です。
解説
それでは、起訴から判決まで、刑事裁判がどのように進むのか、時間軸に沿って具体的に見ていきましょう。
ステージ1:起訴から第一回公判まで【裁判の準備期間】
裁判は、法廷の場で突然に始まるわけではありません。公判に向けた準備期間が重要です。
- 起訴(公判請求)
検察官が裁判所に「起訴状」を提出することで、裁判が始まります。この日から、それまで「被疑者」と呼ばれていた立場は、「被告人」に変わります。 - 弁護人との打ち合わせ
起訴後、裁判所から被告人のもとへ起訴状謄本が届きます。これを受け、弁護人と詳細な打ち合わせを行います。この準備期間が、裁判の行方を左右するといっても過言ではありません。- 認否の決定
起訴状に書かれている内容(公訴事実)を認めるのか、それとも争うのか(否認するのか)を決定します。これが裁判全体の基本方針となります。 - 証拠の検討
検察官が裁判で提出を予定している証拠の一覧を開示請求し、その内容を精査します。不利な証拠にどう反論するか、こちらに有利な証拠はないかなどを検討します。 - 弁護方針の策定
認否や証拠を踏まえ、裁判で何をどのように主張していくか、具体的な戦略を立てます。
- 認否の決定
ステージ2:公判期日【法廷での審理】
いよいよ裁判当日。公判は、主に「冒頭手続」「証拠調べ手続」「論告・弁論」という3つのパートで構成されています。
① 冒頭手続(裁判のオープニング)
- 人定質問
裁判官が、法廷にいるのが間違いなく被告人本人かを確認するため、氏名、生年月日、住所などを尋ねます。 - 起訴状朗読
検察官が立ち上がり、起訴状を読み上げます。これにより、被告人がどのような罪で裁判にかけられているのかが、法廷にいる全員に明確に示されます。 - 黙秘権等の告知
裁判官が被告人に対し、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」といった黙秘権などの権利があることを説明します。 - 罪状認否
裁判の方向性を決める最初の山場です。裁判官が被告人と弁護人に対し、起訴状の内容について認める点、争う点を尋ねます。ここで「間違いありません」と認めれば「自白事件」として、「〜という点は違います」と争えば「否認事件」として、その後の審理が進められます。
② 証拠調べ手続(事実の取り調べ)
- 検察官による冒頭陳述
検察官が、これから証拠によって証明しようとする事実(犯行の動機、計画、実行行為など)のストーリーを説明します。 - 証拠の取り調べ
検察側、弁護側の双方が、それぞれの主張を裏付ける証拠を提出し、その内容を法廷で明らかにしていきます。- 書証・物証
供述調書や実況見分調書、凶器や被害品などが証拠として取り調べられます。 - 証人尋問
事件の目撃者や被害者、専門家などが証人として出廷し、検察官や弁護人の質問に答えます。相手方の証人に対しては、反対尋問を行い、証言の矛盾点や不合理な点を追及します。
- 書証・物証
- 被告人質問
被告人自身が証言台に立ち、弁護人や検察官、そして裁判官からの質問に答えます。これは、被告人が自らの言葉で、事件についての言い分や反省の気持ち、今後の更生の決意などを裁判官に直接伝えることができる、きわめて重要な機会です。
③ 論告・弁論(最終プレゼンテーション)
- 検察官の論告・求刑
証拠調べが終わると、検察官が最終的な意見を述べます。これを「論告」といいます。事実認定と法律解釈についての意見を述べた後、締めくくりとして「よって、被告人を懲役〇年に処するのが相当と思料する」といった形で、相当と考える刑罰の重さを具体的に述べます。これを「求刑」といいます。 - 弁護人の最終弁論
次に、弁護人が被告人のために最後の弁論を行います。無罪を主張する事件であれば検察官の主張の矛盾点を指摘し、罪を認めている事件であれば、示談が成立していることや深く反省していることなど、被告人に有利な事情をすべて挙げ、寛大な判決を求めます。 - 被告人の最終陳述
最後に、被告人自身が話す機会が与えられます。ここで反省や謝罪の言葉、将来への誓いなどを述べて、すべての審理が終了(結審)します。
ステージ3:判決言渡し
結審から約1〜2週間後、判決期日が指定され、再び法廷に呼び出されます。裁判官が判決の主文(「被告人を懲役〇年に処する。この裁判が確定した日から△年間その刑の執行を猶予する」など)と、その結論に至った理由を言い渡します。
弁護士に相談するメリット
刑事裁判という専門的な手続きを、有利に進めるためには弁護士の力が不可欠です。
- 一貫した裁判戦略の立案と実行
起訴前の段階から関与することで、捜査段階の供述との一貫性を保ちながら、最適な弁護方針を立て、裁判の最後まで責任を持って実行します。 - 被告人に有利な証拠の収集・提出
示談書はもちろん、被告人の反省を示す反省文、家族からの嘆願書、再犯防止のための取り組みを示す資料などを準備し、裁判官の心証を良くするための「情状証拠」として効果的に提出します。 - 専門的な法廷技術
検察側の証人に対する鋭い反対尋問や、被告人質問で被告人の人間性や反省の情を効果的に引き出す技術、そして最終弁論での説得力のある主張など、専門家ならではの法廷技術で被告人を弁護します。 - 被告人と家族の精神的支柱
複雑な手続きを分かりやすく説明し、法廷での立ち居振る舞いをアドバイスするなど、裁判という大きなプレッシャーに立ち向かう被告人と、それを見守るご家族を精神的にサポートします。
まとめ
刑事裁判は、厳格なルールと手順に則って進められます。その流れを理解し、各ステップで何をすべきかを把握して万全の準備をすることが、望む結果を得るためには不可欠です。罪を認めるか争うかで、その流れや期間、準備すべきことは大きく異なります。
検察官から起訴されてしまったら、それは専門家である弁護士の助けが絶対に必要になったというサインです。一人で、あるいはご家族だけで悩まず、すぐに刑事裁判の経験が豊富な弁護士に依頼し、信頼できるパートナーとして二人三脚で裁判に臨むことが、あなたとあなたの家族の未来を守るための最善の道です。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に
略式起訴(略式命令)とは?罰金刑で済むケースと拒否する方法
はじめに
検察庁に呼び出され、取り調べの最後に検察官から「この事件は略式(りゃくしき)で進めたいと思いますが、よろしいですね?」と、同意を求められることがあります。
「公開の裁判は避けられる」「罰金を払うだけで終わるらしい」「早く事件を終わらせたい」…そんな思いから、深く考えずに同意書にサインしてしまう方が少なくありません。
しかし、そのサインは、あなたの人生に「前科」を刻むことを意味します。略式起소(略式手続き)は、有罪であることを自ら認めることが大前提の手続きだからです。
この記事では、一見すると手軽で簡単な「略式起訴」とはどのような制度なのか、そのメリットと、見過ごされがちなデメリット、そして安易に同意すべきでないケースと、それを拒否する方法について解説します。
Q&A
Q1. 罰金を払えば、それで終わりで前科はつかないのではないですか?
これは最も多い誤解の一つです。罰金刑も、懲役刑や禁錮刑と同じく、法律上の刑罰であり、有罪判決の一種です。 略式命令によって罰金を支払った場合、その事実は検察庁の管理する犯罪人名簿に記録され、紛れもない「前科」となります。この前科は、特定の職業に就けなくなったり、海外渡航に影響が出たりと、将来の社会生活において様々な不利益をもたらす可能性があります。「罰金=前科なし」では決してありません。
Q2. いったん略式起訴に同意してしまった後で、それを取り消すことはできますか?
検察官の前で同意書にサインしてしまった後でも、検察官が裁判所に略式起訴の請求をする前であれば、同意を撤回することは理論上可能です。しかし、一度同意したものを覆すのは簡単ではありません。また、略式命令が裁判所から出された後でも、その告知を受けてから14日以内であれば、正式な裁判を開くよう請求(正式裁判請求)することができます。ただし、手続きが複雑になるため、同意する前に慎重に判断することが何よりも重要です。
Q3. 略式起訴を拒否したら、どうなるのですか?必ず刑が重くなりますか?
略式起訴を拒否すると、検察官は通常の刑事裁判を求める「公判請求」を行うことになります。つまり、公開の法廷で審理されることになります。これを恐れて同意してしまう方が多いのですが、正式裁判になったからといって、必ずしも罰金刑より重い刑罰が科されるわけではありません。 裁判官が検察官の主張に縛られずに判断するため、逆に罰金額が低くなる可能性や、無罪となる可能性さえあります。もちろん、事案によってはより重い判断が下されるリスクもゼロではありませんが、「拒否=不利益」と短絡的に考えるべきではありません。
解説
「罰金で済むなら」という安易な判断が、取り返しのつかない結果を招くこともあります。略式起訴の正体について、詳しく見ていきましょう。
略式起訴(略式手続き)の仕組みとは?
略式起訴とは、検察官が「100万円以下の罰金または科料」が相当と判断した比較的軽微な事件について、被疑者の同意を得て、公開の裁判を開かずに書面審理のみで罰金刑を求める手続きのことです。正式名称を「略式手続」といいます。
その流れは以下の通りです。
- 検察官による説明と同意の確認
検察官が被疑者に対し、略式手続きの内容を説明し、異議がないかを確認します。被疑者が同意すると、その旨を記載した書面に署名・押印します。 - 検察官による略式起訴
検察官が簡易裁判所に対し、捜査書類とともに略式命令を出すよう請求(起訴)します。 - 裁判官による書面審理
裁判官は法廷を開かず、検察官から提出された書類のみを見て、罰金の額などを判断します。 - 略式命令の発付
裁判所から被疑者(この時点から被告人)の自宅などに、「略式命令」と書かれた書面と罰金の納付書が郵送されてきます。 - 罰金の納付
指定された期限内に罰金を納付すれば、すべての刑事手続きは終了です。
この手続きの最大の特徴は、①公開の裁判がないこと、②スピーディーに終わること、③本人の言い分を聞く場がないことです。
メリットと、知っておくべき重大なデメリット
略式起訴には、一見すると魅力的なメリットがあります。しかし、その裏には重大なデメリットが隠されています。
メリット
- 手続きの迅速性
起訴から命令発付まで数週間程度で終わり、事件を早期に終結させることができます。 - 身体拘束からの解放
逮捕・勾留中に略式起訴された場合、罰金を納付(または仮納付)すれば、その日のうちに釈放されることがほとんどです。 - プライバシーの保護
公開の法廷に出る必要がないため、裁判の傍聴などを通じて事件のことが他人に知られるリスクを低減できます。
デメリット
- 【最重要】100%、有罪・前科となる
これが最大のデメリットです。略式手続きは、被疑者が罪を認めていることが前提です。そのため、無罪になることは絶対にありません。 略式命令は有罪判決と同じ効力を持ち、罰金刑という「前科」があなたの経歴に記録されます。 - 反論の機会がない
書面審理のみで進むため、公開の法廷で「それは事実と違う」と反論したり、「酌むべき事情があった」と情状を訴えたりする機会が一切ありません。検察官の作成したストーリーが、そのまま事実として認定されてしまいます。 - 証拠を争えない
検察官が提出した証拠について、その信用性を争うことができません。例えば、不当な取り調べによって作成された供述調書があったとしても、それがそのまま有罪の証拠として採用されてしまいます。
略式起訴に同意すべきでないケース
以上のデメリットを踏まえると、以下のようなケースでは、安易に略式起訴に同意すべきではありません。
- ケース1:無実を主張したい場合(否認事件)
言うまでもありませんが、やっていない罪で略式起訴を打診された場合は、絶対に同意してはいけません。 同意することは、無実の主張を自ら放棄し、無実の罪で前科を背負うことを意味します。 - ケース2:事実関係に争いがある場合
大筋で罪を認めていても、その内容に納得できない点がある場合も同様です。
(例)「盗んだのは事実だが、被害額は検察官が言う金額よりずっと少ない」
このような場合、略式起訴に同意すると、あなたの言い分は一切考慮されず、検察官の主張する事実(高額な被害額等)がそのまま認定されてしまいます。 - ケース3:罰金額や刑の重さに不満がある場合
罰金額に納得がいかない場合や、正式な裁判で情状を尽くせば、より軽い処分(例えば罰金額の減額)が見込める場合も、拒否を検討する価値があります。
略式起訴を拒否する方法と、その後の流れ
では、略式起訴を拒否したい場合、どうすればよいのでしょうか。
- 拒否の方法
検察官に対して、「略式手続きには同意しません。正式な裁判を求めます」と、明確な言葉で意思表示をしてください。そして、同意書への署名・押印を断りましょう。 - 拒否した後の流れ
あなたが略式起소を拒否すると、検察官は通常の刑事裁判(公判)を求める「公判請求」をすることになります。その後は、起訴状が自宅に届き、約1~2ヶ月後に公開の法廷で第一回公判が開かれる、という通常の刑事裁判の流れに乗ります。そこでは、弁護人と共に、無罪を主張したり、有利な情状を訴えたりすることが可能になります。
弁護士に相談するメリット
検察官から略式起訴を打診された場面でこそ、弁護士の存在が大きな意味を持ちます。
- 同意すべきか否かの的確な法的アドバイス
弁護士は、事件の証拠関係や事案の性質を分析し、略式起소に応じた場合のメリット・デメリットと、正式裁判で争った場合の見通し(無罪の可能性、刑罰の相場など)を具体的に示します。その上で、あなたがどちらを選択すべきか、専門的な視点から的確にアドバイスします。 - 検察官との交渉
略式起訴を打診される前に、弁護士が検察官と交渉し、そもそも不起訴(起訴猶予)にできないか働きかけます。また、仮に略式起訴が避けられない場合でも、罰金額が少しでも低くなるよう交渉することもあります。 - 正式裁判での徹底した弁護活動
略式起소を拒否し、正式裁判に臨むと決めた場合、弁護士はあなたの代理人として、法廷で無罪を主張したり、有利な証拠を提出したりと、最善の判決を得るために全力で戦います。
まとめ
略式起訴は、「罰金だけで早く終わる」という手軽さの裏に、「100%有罪となり前科が付く」「一切の反論ができない」という、取り返しのつかないデメリットが潜んでいます。
特に、無実を主張している方や、事実関係に争いがある方は、安易に同意してはいけません。検察官から略式起訴を打診されたら、その場で即決するのではなく、「弁護士と相談してから決めさせてください」と伝え、必ず一度持ち帰って専門家の意見を聞くようにしてください。
その一呼吸が、あなたの人生に不利益な「前科」が刻まれるのを防ぐ、最後の防波堤となります。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に
起訴・不起訴はいつ決まる?検察官の判断基準と不起訴処分の種類
はじめに
警察や検察の捜査を受けた方、またそのご家族にとって、最大の関心事は「起訴されるのか、それとも不起訴になるのか」という点ではないでしょうか。この起訴・不起訴の決定は、単に裁判が開かれるかどうかを決めるだけでなく、その後の人生に「前科」が付くかどうかが決まる、きわめて重大な分岐点です。
この重要な判断を、日本の刑事司法制度において一身に担っているのが「検察官」です。検察官は、どのような情報を基に、どのような考え方でこの重い判断を下しているのでしょうか。
この記事では、刑事事件における最終処分である「起訴」「不起訴」がいつ、どのような基準で決定されるのか、そして不起訴処分にはどのような種類があるのかについて解説します。
Q&A
Q1. 捜査が終わってから、どのくらいの期間で起訴・不起訴が決まりますか?
これは、身柄が拘束されているか(身柄事件)、されていないか(在宅事件)によって大きく異なります。
- 身柄事件の場合
逮捕・勾留されている事件では、勾留期間の満了日(逮捕から最長で23日目)までに、検察官は必ず起訴・不起訴を決定しなければなりません。法律で厳格な時間制限が定められています。 - 在宅事件の場合
明確な時間制限はありません。警察から事件が検察庁に送られてから(書類送検)、数ヶ月で決まることもあれば、事案が複雑な場合は1年以上かかることもあります。この「いつ決まるか分からない」という点が、在宅事件の当事者にとって大きな精神的負担となります。
Q2. 不起訴になったら、その理由を教えてもらえますか?
検察官は、不起訴処分を下した際に、その理由を被疑者に詳しく説明する義務はありません。そのため、なぜ不起訴になったのか分からないまま事件が終了することも多いです。しかし、弁護士がついていれば、担当検察官に問い合わせることで、大まかな理由(例えば、示談が成立したことが決め手になった、など)を確認できる場合があります。また、被疑者は検察官に対して「不起訴処分告知書」という、不起訴になった事実を証明する書面の交付を請求することができます。
Q3. 一度不起訴になった事件で、再び捜査されたり起訴されたりすることはありますか?
判決が確定した場合の「一事不再理」とは異なり、不起訴処分には、法律上、事件を完全に蒸し返させないという効力(確定力)はありません。そのため、例えば不起訴になった後に新たな有力な証拠(犯行を決定づけるDNA鑑定の結果など)が見つかったような例外的なケースでは、再び捜査が開始され、起訴される可能性はゼロではありません。しかし、これは稀なケースであり、実務上は、一度不起訴処分となった事件が再燃することは、あまりないと考えてよいでしょう。
解説
日本の刑事手続きのゴールともいえる、検察官の「終局処分」。その内実を詳しく見ていきましょう。
起訴・不起訴の全権を握る「検察官」
まず、検察官とはどのような役割を担う存在なのかを理解することが重要です。検察官は、主に警察から送致された事件について、自らも捜査を行い、証拠を精査し、被疑者を刑事裁判にかけるかどうか(=起訴するかどうか)を決定する権限を持ちます。
日本では、この起訴する権限(公訴権)は検察官が独占しており、警察官や裁判官、もちろん被害者も、誰かを起訴することはできません。この検察官の強大な権限を「公訴権の独占」といいます。つまり、刑事事件の入口が警察による捜査だとすれば、裁判という次のステージに進む門番が検察官なのです。
検察官は、何を基準に「起訴」「不起訴」を判断するのか?
検察官は、単なる機械のように「法律の要件に当てはまれば即起訴」という判断をしているわけではありません。刑事訴訟法第248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と定められています。
これは「起訴便宜主義」と呼ばれ、検察官に広い裁量権を与えています。検察官は、主に以下の2つの側面から、事件を総合的に判断します。
判断基準①:嫌疑の程度(裁判で有罪にできるか?)
第一の基準は、被疑者が罪を犯したことが、集められた証拠によって間違いなく証明できるか、という点です。検察官は、法廷で裁判官を納得させ、有罪判決を得られるだけの客観的証拠(物証、防犯カメラ映像など)や関係者の供述証拠が揃っているかを厳しく吟味します。
もし、証拠が不十分で、裁判で無罪になる可能性が高いと判断すれば、検察官は起訴しません。これが後述する「嫌疑不十分」による不起訴処分です。
判断基準②:処罰の必要性(あえて裁判にかける必要があるか?)
第二の基準は、たとえ有罪にできるだけの十分な証拠があったとしても、「あえて起訴して刑事罰を科すまでの必要性があるか」という点です。これこそが、検察官の裁量が最も大きく働く部分であり、弁護活動が最も重要となるポイントです。
検察官は、主に以下のような事情を天秤にかけ、処罰の必要性を判断します。
- 犯罪自体の重さ
被害額の大小、犯行態様の悪質性、計画性の有無など。 - 被疑者側の事情
年齢、これまでの生活態度、前科・前歴の有無、事件に至った経緯、反省の深さなど。 - 被害者側の事情
被害の程度、被害者の処罰感情の強弱など。 - 犯罪後の状況
被害者との示談が成立しているか、被害弁償が尽くされているか、被疑者が再犯防止に向けて具体的に努力しているか(例えば、依存症の治療を開始したなど)。
これらの事情を総合的に考慮した結果、検察官が「今回は起訴するまでの必要はない」と判断した場合、「起訴猶予」という不起訴処分が下されます。
知っておきたい「不起訴処分」の3つの種類
「不起訴」と一言でいっても、その理由は様々です。いずれの場合も前科は付きませんが、その内容は大きく異なります。
- ① 嫌疑なし
捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合や、犯罪の成立を証明する証拠がない場合です。いわゆる「白」であり、無実が証明されたことを意味します。 - ② 嫌疑不十分
犯罪の疑いはあるものの、それを裁判で立証するための証拠が不十分な場合です。「黒とは言い切れないグレー」の状態で事件が終了するイメージです。否認事件で、自白が取れず、客観的証拠も乏しいケースなどがこれにあたります。 - ③ 起訴猶予
実務上の不起訴処分の大多数を占めるのが、この起訴猶予です。 嫌疑は十分にあり、起訴すれば有罪にできるけれども、上記で解説した様々な事情を考慮し、検察官が「今回は大目に見ましょう」と起訴を見送る処分です。罪を認めている事件で、被害者との示談が成立している場合などは、この起訴猶予を目指すことになります。
弁護士に相談するメリット
検察官が下す起訴・不起訴の判断、特に「起訴猶予」を勝ち取るためには、弁護士による専門的な活動が不可欠です。
- 検察官の判断材料に直接働きかける活動
弁護士の最大の役割は、検察官が判断基準とする「処罰の必要性」を低下させるための活動を行うことです。具体的には、被害者がいる事件であれば、迅速に示談交渉を開始し、被害弁償を尽くすことで、被害者の処罰感情を和らげます。そして、示談が成立したことを示す示談書を検察官に提出します。 - 有利な情状を意見書として提出
被疑者が深く反省していること、家族が今後の監督を誓約していること、再犯防止のための具体的な取り組みを始めていることなど、本人に有利な事情を「意見書」としてまとめ、説得力のある形で検察官に伝えます。口頭で伝えるだけでなく、証拠に基づいた書面として提出することが重要です。 - 検察官との直接交渉
弁護士は、担当検察官と直接面談し、事件の見通しや検察官の心証を探りながら、なぜ本件が不起訴処分(起訴猶予)にすべき事案であるかを法的な観点から主張します。
まとめ
刑事事件の最終的なゴールの一つは、前科が付くことを回避する「不起訴処分」の獲得です。その鍵を握るのは、検察官ただ一人です。
そして、検察官の判断は、「証拠が十分か」という点に加え、「あえて起訴する必要があるか」という、情状面を考慮した裁量に大きく委ねられています。この裁量判断にプラスに働くよう、いかに有効な活動を行えるかが、弁護士の腕の見せ所となります。
被害者との示談、反省の態度の表明、再犯防止策の提示。これらの活動は、検察官が処分を決定する前に行わなければ意味がありません。警察の捜査が始まった段階、あるいは検察に事件が送られた段階で、一日も早く弁護士に相談し、不起訴処分獲得に向けた活動を開始することが、あなたの未来を守るために最も重要なことです。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に
在宅事件とは?逮捕されない場合の流れと注意点を弁護士が解説
はじめに
「刑事事件」と聞くと、多くの方がテレビドラマのように、警察官に逮捕され、手錠をかけられて連行される…という場面を想像するかもしれません。しかし、全ての刑事事件で身柄が拘束されるわけではありません。被疑者の身柄を拘束せずに、自宅で普段通りの生活を送りながら捜査が進められる「在宅事件」というケースも、実は数多く存在するのです。
警察から連絡があり取り調べを受けたものの、逮捕はされずに家に帰された。「逮捕されなかったのだから、もう大丈夫だろう」「事件はこれで終わりだ」と安心してしまう方が少なくありません。
しかし、その考えは大きな誤解です。在宅事件は、決して事件が終了したわけではありません。何も対策をせずに放置していると、ある日突然、検察庁から呼び出され、起訴されて刑事裁判になり、前科が付いてしまう可能性があります。
この記事では、「在宅事件」とは具体的にどのようなものか、どのような流れで手続きが進むのか、そして「逮捕されないからこそ」注意すべき重要なポイントについて解説します。
Q&A
Q1. 在宅事件になったら、もう今後、逮捕されることはないのですか?
いいえ、絶対に逮捕されないという保証はありません。 在宅事件として捜査が始まった後でも、警察からの出頭要請に正当な理由なく応じなかったり、被害者や証人に接触して証拠隠滅を疑われるような行動をとったりすると、「逃亡または証拠隠滅のおそれあり」と判断され、逮捕状が請求されて逮捕されてしまう可能性があります。在宅事件であるからこそ、捜査には誠実に対応する必要があります。
Q2. 在宅事件の捜査期間はどのくらいですか?いつ終わるか分からず不安です。
在宅事件には、逮捕・勾留されている事件のような厳格な時間制限がありません。 そのため、捜査が長期化する傾向があり、事件が検察官に送られてから最終的な処分が決まるまで、数ヶ月から、場合によっては1年以上かかることもあり得ます。この「いつ終わるか分からない」という状況が、在宅事件の被疑者にとって大きな精神的負担となります。弁護士に依頼することで、捜査の進捗状況を担当検察官に確認し、見通しを立てることが可能になります。
Q3. 在宅事件でも、前科が付く可能性はあるのですか?
はい、十分にあります。 「在宅事件=軽い事件」とは限りません。捜査の結果、検察官が「刑事裁判にかける必要がある」と判断すれば、起訴されます。そして、裁判で有罪判決(罰金刑や執行猶予付き判決も含む)が確定すれば、逮捕された事件と同様に「前科」が付きます。前科をつけないためには、検察官が起訴・不起訴を決定する前に、不起訴処分を勝ち取るための弁護活動を行うことが重要です。
解説
「逮捕されていないから大丈夫」という油断は禁物です。在宅事件の正しい知識を身につけ、適切な対応を取りましょう。
在宅事件とは?- 逮捕されない刑事事件のリアル
在宅事件とは、法律上の正式な用語ではありません。逮捕・勾留によって身柄を拘束されている「身柄事件」と区別するために、実務上使われている言葉です。その名の通り、被疑者が自宅で日常生活を送りながら、警察や検察からの呼び出しに応じて取り調べを受ける形で捜査が進んでいきます。
では、どのような場合に在宅事件になるのでしょうか。主に、捜査機関が「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断した場合です。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 犯罪事実が比較的軽微である(例:被害額の少ない万引き、全治数日の軽傷な暴行など)
- 被疑者が事実関係を概ね認めている
- 定職に就き、安定した収入がある
- 家族と同居しており、監督が期待できる
- 被害者との間で示談が進んでいる、または示談の可能性がある
最初から逮捕されずに在宅事件として扱われるケースのほか、一度逮捕されたものの、検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留請求を却下したりして釈放され、その後の捜査が在宅事件に切り替わるケースもあります。
在宅事件の具体的な流れ
在宅事件は、身柄事件とは異なり、時間制限なく進行します。
- ステップ①:警察からの呼び出しと取り調べ
ある日、警察署の担当刑事から電話があり、「〇〇の件で少しお話を伺いたいので、ご都合の良い日に警察署まで来てください」といった形で呼び出しを受けます。この出頭は法律上「任意」ですが、前述の通り、正当な理由なく拒否し続けると逮捕されるリスクがあります。指定された日に出頭し、取調室で事件に関する取り調べを受け、供述調書が作成されます。この呼び出しは、一度だけでなく、捜査の進展に応じて複数回にわたることが一般的です。 - ステップ②:検察官への送致(いわゆる「書類送検」)
警察での捜査が一通り終わると、警察は事件に関する証拠や書類一式を検察庁に送ります。これを「送致(そうち)」といい、ニュースなどでよく聞く「書類送検」は、この在宅事件の送致を指します。被疑者の身柄は送られないため、この時点では日常生活に何の変化もありません。しかし、事件の捜査の主体が警察から検察官に移り、最終処分に向けて手続きが大きく前進したことを意味します。 - ステップ③:検察官からの呼び出しと取り調べ
事件の送致を受けると、今度は担当の検察官から呼び出しがあります。検察官は、警察が作成した捜査記録を精査し、自らも被疑者を取り調べて、起訴するかどうかを最終的に判断します。 - ステップ④:検察官による最終処分(起訴・不起訴)の決定
検察官は、すべての捜査結果を踏まえ、被疑者を刑事裁判にかける「起訴」とするか、裁判にはかけずに事件を終了させる「不起訴」とするかを決定します。
- 起訴
正式な裁判(公判請求)を求めるか、簡易的な手続きである「略式起訴(罰金刑)」を求めるかに分かれます。いずれも有罪となれば前科が付きます。 - 不起訴
嫌疑不十分、起訴猶予などの理由で、事件はここで完全に終了します。もちろん前科は付きません。在宅事件における最大の目標は、この不起訴処分を獲得することです。
在宅事件だからこそ注意すべき3つのポイント
身体拘束というプレッシャーがない分、在宅事件には特有の「落とし穴」があります。
注意点1:不利な供述をしないこと
身柄を拘束されていない解放感から、つい気が緩み、取り調べで安易な受け答えをしてしまいがちです。しかし、在宅事件であっても、そこで作成される供述調書の証拠としての重要性は、身柄事件と何ら変わりません。 一度署名・押印してしまえば、その内容を後から覆すのはきわめて困難です。警察からの呼び出しを受ける前に、弁護士に相談し、どのようなことを聞かれそうか、どのように答えるべきかをしっかりと準備しておくことが、自分を守るために不可欠です。
注意点2:被害者との示談交渉を放置しないこと
在宅事件になったということは、示談交渉を進めるための時間は十分にあります。この時間を有効活用しない手はありません。特に、万引きや暴行事件など被害者がいる犯罪では、被害者との示談が成立しているかどうかが、検察官が起訴・不起訴を判断する上で最も重要な要素の一つとなります。逮捕されていないからと安心し、示談交渉を放置していると、被害者の処罰感情が高いままで検察官に事件が送られ、起訴されてしまうリスクが高まります。
注意点3:捜査機関からの呼び出しを無視しないこと
仕事が忙しい、気まずいなどの理由で、警察や検察からの出頭要請を無視したり、理由なく断り続けたりするのは最悪の対応です。これは捜査への非協力的な態度と見なされ、「逃亡のおそれあり」として逮捕状を請求される直接的な原因になりかねません。どうしても都合が悪い場合は、正直にその旨を伝えて日程を調整してもらいましょう。弁護士に依頼すれば、こうした日程調整も代理人として行うことができます。
弁護士に相談するメリット
在宅事件こそ、早期に弁護士に相談することで、得られるメリットは大きくなります。
- 不起訴処分の獲得に向けた活動
在宅事件における弁護士の最大の目標は、前科のつかない「不起訴処分」を得ることです。そのために、被害者との示談交渉を代理人として迅速かつ円滑に進めます。また、本人の反省の深さや、ご家族による監督、再犯防止への具体的な取り組みなどをまとめた意見書を検察官に提出し、寛大な処分を求めます。 - 取り調べへの的確なアドバイスと同行
警察や検察からの呼び出しの前に、想定される質問への回答シミュレーションを行い、不利な供述調書が作成されるのを防ぎます。必要に応じて取り調べに同行し、不当な追及からご本人を守ります。 - 捜査機関との窓口機能
弁護士があなたと捜査機関との間の窓口となることで、今後の手続きの見通しを把握しやすくなり、「いつ終わるか分からない」という精神的な負担が軽減されます。出頭日時の調整なども弁護士に任せることができます。 - 平穏な日常生活の維持
弁護活動を弁護士に任せることで、あなたは仕事や学業、家庭生活など、普段通りの生活の維持に集中することができます。これは、在宅事件のメリットを活かすことにつながります。
まとめ
在宅事件は、逮捕されないからといって、決して安心できる状況ではありません。捜査は水面下で着実に進んでおり、起訴されれば、逮捕された事件と同じように前科が付いてしまうというリスクを常に抱えています。
このリスクを回避し、前科をつけずに事件を解決するためには、検察官が最終処分を下す前に、いかに有効な弁護活動を行えるかにかかっています。特に、被害者との示談成立は、不起訴処分を得るための最重要課題です。
幸い、在宅事件には、弁護士とじっくり相談し、対策を練るための時間があります。警察から事件について連絡が来たら、それは「油断してはいけない」というサインです。お早めに弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。万全の準備で捜査に臨むことが、あなたの未来を守ります。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に
接見禁止とは?家族が面会できない場合の対処法と弁護士の役割
はじめに
ご家族が逮捕されたと聞き、心配でたまらず警察署に駆けつけたものの、「接見禁止(せっけんきんし) が付いているので、ご家族でも会えません」と、面会を断られてしまうことがあります。
なぜ会えないのか、本人は中でどうしているのか、何も分からず、ただ時間だけが過ぎていく。このような状況は、ご家族にとって、耐えがたいほどの不安と無力感をもたらします。
この「接見禁止」は、特に共犯者がいる組織的な犯罪や、本人が容疑を否認している事件などで、裁判官によって下される厳しい処分です。
この記事では、この接見禁止とは一体どのような処分なのか、なぜ家族ですら面会できなくなるのか、そして、その絶望的な状況の中でご家族ができることと、弁護士が果たすべき重要な役割について解説していきます。
Q&A
Q1. なぜ血のつながった家族なのに、面会を禁止されるのですか?
裁判官が接見禁止を決定するのは、「証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がある」と判断した場合です。たとえ家族であっても、面会時に事件に関する口裏合わせをしたり、外部の共犯者に指示を伝えたりする可能性がゼロではない、と捜査機関や裁判官が懸念するのです。特に、振り込め詐欺のような組織犯罪や、複数人での暴行事件など、まだ逮捕されていない共犯者がいるケースでは、接見禁止が付きやすい傾向にあります。これは家族を疑っているというより、事件の真相解明のためにあらゆる証拠隠滅の可能性を排除したい、という捜査上の要請が強く働くためです。
Q2. 接見禁止は、いつまで続くのでしょうか?
接見禁止の期間は、法律で明確に定められているわけではありません。原則として、勾留が続いている間は、接見禁止も継続される可能性があります。つまり、勾留が延長されれば最長で20日間、さらに起訴された後も、裁判が終わるまで接見禁止が続くケースもあります。ただし、弁護士が後述する「準抗告」や「一部解除の申し立て」を行うことで、途中で解除されたり、家族のみ面会が許可されたりする可能性は十分にあります。
Q3. 接見禁止中でも、手紙のやり取りや差し入れはできますか?
接見禁止の決定が出ると、原則として手紙のやり取り(信書の発受)も禁止されます。差し入れについては、現金や衣類、本などは認められることが多いですが、手紙やメモなどをこっそり忍ばせることはできません。発覚した場合は、証拠隠滅を図ったと見なされ、ご本人にとってもご家族にとっても、さらに状況が悪化する恐れがあります。唯一の例外は、弁護士を介する方法です。弁護士が内容を確認し、証拠隠滅の恐れがないと判断した上で、ご家族からの手紙をご本人に渡すことは可能です。
解説
外部との繋がりを絶たれてしまう「接見禁止」。その内容と対処法について、より深く理解していきましょう。
接見禁止とは?- 弁護士以外、誰とも会えない孤立した状況
接見禁止とは、正式には「接見等禁止決定」と呼ばれる、裁判官による命令です。この決定が下されると、被疑者・被告人は、弁護士以外の全ての者と、以下の行為を禁じられます。
- 接見
直接会って話をすること。 - 書類や物の授受
手紙以外の物(メモなども含む)を受け取ったり渡したりすること。 - 信書の発受
手紙をやり取りすること。
つまり、ご家族、友人、恋人、会社の同僚など、弁護士資格を持つ者以外とは、会うことも、手紙を出すことも、受け取ることもできなくなります。逮捕された本人は、外部の世界から遮断され、たった一人で捜査官と向き合わなければならない、過酷で孤立した状況に置かれるのです。
接見禁止が付きやすい事件の類型
裁判官は、どのような場合に「証拠隠滅の恐れ」が強いと判断し、接見禁止の決定を下すのでしょうか。実務上、特に接見禁止が付きやすいとされる事件の典型例は以下の通りです。
- 共犯者がいる事件
振り込め詐欺(特殊詐欺)、強盗、複数人による暴行・傷害など、組織的・計画的に行われた犯罪では、接見禁止が付けられる可能性が高いといえます。外にいる共犯者と、面会に来た家族や知人を介して口裏合わせをしたり、証拠の隠蔽を指示したりすることを防ぐのが最大の目的です。 - 否認事件
被疑者が容疑を全面的に否認している事件でも、接見禁止が付きやすくなります。捜査機関は、被疑者が外部の協力者と連絡を取り、被害者を威圧して被害届を取り下げさせたり、アリバイ工作をしたりすることを強く警戒するためです。 - 薬物事件
覚せい剤や大麻などの薬物事件、特に営利目的での密売や栽培が疑われるケースでは、密売グループの他のメンバーや入手ルートに関する情報を隠蔽するため、関係者との連絡を遮断する目的で接見禁止が付けられることが多くあります。 - 暴力団が関与する事件
組織的な犯罪であり、被害者への報復や脅迫の危険性も高いため、ほぼ全てのケースで接見禁止の措置が取られます。
ご家族がすべきこと、すべきでないこと
接見禁止という厳しい壁に直面したとき、ご家族にできることは限られていますが、何もしないでいるわけではありません。
【ご家族ができること】
- 弁護士に依頼する
弁護士は、接見禁止の影響を受けずに本人と自由に面会できます。本人との唯一の連絡役を担い、状況を正確に把握し、家族のメッセージを伝えることができます。 - 差し入れをする
衣類、現金、本、便箋、切手などの差し入れは、接見禁止中でも通常通り可能です。留置施設での生活を支えるために、必要なものを差し入れてあげましょう。
【ご家族がすべきでないこと】
- 独自に被害者と接触しようとすること
早く示談したいという気持ちは分かりますが、ご家族が直接被害者に連絡を取ろうとすることは、証拠隠滅(脅迫・懐柔)を疑われる原因となり、接見禁止が長引く最悪の事態を招きかねません。示談交渉は必ず弁護士に任せてください。 - 差し入れに手紙を紛れ込ませること
発覚すれば、ご家族も証拠隠滅等に加担したと見なされるリスクがあり、状況はさらに悪化します。
接見禁止を解除するための弁護活動
接見禁止は、一度決定されたら裁判が終わるまで解除されない、というわけではありません。弁護士は、この厳しい処分に対して、法的な手続きを通じて解除を求めて戦うことができます。
- 準抗告(じゅんこうこく)
接見禁止決定そのものが不当であるとして、裁判所に不服を申し立てる手続きです。「共犯者はすで全員逮捕されている」「家族は事件と無関係で口裏合わせの危険はない」といった事情を主張し、決定の取り消しを求めます。 - 接見禁止の一部解除の申し立て
「全ての人との接見を禁じる必要はない」として、ご家族など特定の人物に限定して接見禁止を解くよう求める、より現実的で認められやすい申し立てです。例えば、「夫の会社の退職手続きについて相談するため、妻との接見を許可してほしい」「高齢の母親を安心させるため、母親との面会だけでも認めてほしい」など、面会の具体的な必要性を説得的に主張します。
弁護士に相談するメリット
接見禁止という厳しい状況において、弁護士の存在は、ご本人とご家族によって力となります。
- 唯一のコミュニケーション手段の確保
弁護士は、ご本人と外部をつなぐ唯一のパイプ役です。ご本人の健康状態や精神状態、事件に対する考えなどを家族に伝え、家族からの励ましや必要な情報を本人に届けることで、心の孤立を防ぎ、精神的な支えとなります。 - 接見禁止解除に向けた活動
上記で解説した「準抗告」や「一部解除の申し立て」といった法的な手続きを、迅速かつ的確に行うことができます。家族との面会を実現するために活動します。 - 捜査機関への牽制
弁護士が頻繁に接見に訪れること自体が、捜査機関に対する無言の圧力となり、自白の強要や不当な取り調べを抑止する効果が期待できます。 - ご家族の不安の軽減
先の見えない状況で不安を抱えるご家族に対し、事件の今後の見通しや、今すべきことを具体的にアドバイスすることで、精神的な負担を軽減し、冷静な対応ができるようサポートします。
まとめ
接見禁止は、逮捕されたご本人を社会から完全に隔離し、精神的に追い詰める、きわめて厳しい処分です。特に共犯者のいる事件や否認事件では、この処分が下される可能性が高く、ご家族の不安は計り知れないものとなります。
しかし、このような状況でこそ、弁護士の真価が発揮されます。弁護士は、ご本人とご家族をつなぐ唯一の架け橋であり、接見禁止の解除に向けて法的に争うことができる存在です。
もしあなたの大切なご家族が逮捕され、接見禁止となってしまったら、どうか諦めないでください。一刻も早く刑事事件を扱う弁護士に相談し、まずは本人とのコミュニケーションルートを確保することが、この困難な状況を乗り越えるための、重要で確実な第一歩となります。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に
警察の取り調べで不利にならないための黙秘権の使い方とは?
はじめに
もし、あなたやご家族が逮捕されてしまったら、その後の「取り調べ」が刑事事件全体の行方を左右する、きわめて重要な局面となります。閉鎖的な取調室で、連日、捜査のプロである警察官から厳しい追及を受け続けると、誰でも冷静な判断が難しくなります。その結果、意図せず自分に不利な内容を話してしまい、それらが「供述調書」という証拠になってしまうケースは後を絶ちません。
このような絶体絶命ともいえる状況で、ご自身を守るための最も強力な武器、それが憲法で保障された「黙秘権(もくひけん)」です。しかし、この権利もただ行使すればよいというものではありません。使い方を間違えると、かえって事態を悪化させる可能性すらあります。
この記事では、黙秘権とはそもそも何なのか、どのような場面で、どのように使うのが効果的なのか、そして黙秘権を行使する際の注意点について解説します。
Q&A
Q1. 黙秘権を使うと「反省していない」と思われて、かえって不利になりませんか?
これは非常に多くの方が抱く疑問であり、また捜査官がそのように誘導してくる典型的な言葉です。結論から言うと、黙秘権を行使したこと自体を理由に、裁判で刑が重くなることはありません。黙秘権は、不当な自白の強要から国民を守るための正当な権利です。ただし、罪を認めている事件で、反省の情を示すことが有利な情状となり得るのも事実です。そのため、事件の内容に応じて、完全に黙秘するのか、部分的に話すのかを戦略的に判断することが重要になります。
Q2. どのタイミングで黙秘権を使えばいいのでしょうか?
黙秘権は、取り調べの最初から最後まで、いつでも行使できます。特に、①無実の罪を疑われている(否認事件)、②容疑は認めているが事実関係の一部に争いがある、③逮捕直後で精神的に動揺し、冷静に話せる状態ではない、といったケースでは、黙秘権の行使を積極的に検討すべきです。安全な方法としては、弁護士と接見し、今後の供述方針を固めるまでは黙秘権を行使することです。「弁護士が来るまで一切話しません」と明確に伝えるのが効果的です。
Q3. 黙秘権を使ったら、本当に何もかも話さなくていいのですか?
はい、その通りです。事件に関する質問に対しては、一切答える義務はありません。氏名や生年月日といった、事件とは直接関係のない人定事項についても、答える義務はないとされています。ただし、実務上は、氏名などを話すことで円滑なコミュニケーションのきっかけとすることもあります。重要なのは、「何を話し、何を話さないか」をご自身でコントロールできる点です。完全に黙る「完黙」だけでなく、話したいことだけを話す「選択的供述」も可能です。
解説
それでは、あなたを守る盾となる「黙秘権」について、さらに詳しく見ていきましょう。
黙秘権とは?- あなたに保障された「話さない権利」
黙秘権は、憲法第38条1項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められている、国民に保障された基本的人権の一つです。また、刑事訴訟法では、取り調べの前に、警察官や検察官が被疑者に対して黙秘権があることを告げなければならないと義務付けられています。
この権利の目的は、かつて捜査機関による拷問や脅迫によって、無実の人が嘘の自白を強要され、えん罪が生まれてしまった歴史への反省から、個人の人権を守ることにあります。
黙秘権の行使の仕方は、主に以下の3つのパターンに分けられます。
- 完全黙秘(完黙)
取り調べの最初から最後まで、事件に関する一切の質問に対して黙り続ける方法です。特に、やっていない罪で疑われている否認事件で有効です。 - 一部黙秘
大筋で容疑を認めているものの、犯行の経緯や動機など、一部納得できない部分についてのみ供述を拒否する方法です。 - 選択的供述
捜査官の質問に答える形ではなく、自分が話したいこと、主張したいことだけを一方的に話す方法です。
どの方法を選択すべきかは、事件の内容や今後の弁護方針によって異なります。
黙秘権を使うべき具体的な3つのケース
黙秘権は強力な権利ですが、やみくもに使えば良いわけではありません。戦略的な視点が不可欠です。ここでは、黙秘権の行使を特に検討すべき3つのケースをご紹介します。
ケース1:無実の罪を疑われている場合(否認事件)
これは、黙秘権が最もその価値を発揮する場面です。捜査機関は、あなたを「犯人である」という前提で取り調べを進め、そのストーリーに合致する供述を引き出そうとします。
もしあなたが無実を訴えても、不用意に様々なことを話してしまうと、その発言の一部だけを切り取られたり、揚げ足を取られたりして、あたかも罪を認めたかのような、あるいは状況に矛盾があるかのような供述調書を作成されてしまうリスクがあります。
例えば、「現場の近くには行ったが、やっていない」と話したとします。すると、「被疑者は、犯行現場付近にいたことは認めている」という部分だけが強調された調書が作られかねません。
このような事態を防ぐため、否認事件では、弁護士と今後の対応を協議できるまで完全黙秘を貫くのが一つの戦略となります。
ケース2:罪を認めているが、内容に争いがある場合
罪自体は認めていても、その詳細な内容について捜査機関の認識と食い違いがある場合も、黙秘権は有効です。
- 傷害事件の例
相手に殴られたので殴り返した(正当防衛を主張したい)が、捜査官は一方的な暴行と決めつけている。
このような場合、争いのない事実(相手と接触があったことなど)は認めたうえで、争点となる部分(正当防衛の状況、故意の有無など)については、弁護士と相談するまで話さない、という「一部黙秘」が有効な戦略となります。
ケース3:記憶が曖昧、または精神的に動揺している場合
逮捕という非日常的な事態に直面し、精神的に動揺している中で行われる取り調べは、きわめて危険です。記憶が混乱しているのに、捜査官に促されるままに曖昧な供述をしてしまうと、それが確定的な事実として調書に残ってしまいます。
このような時は、無理に話す必要は全くありません。「今は動揺していて、冷静に話せる状態ではありません。弁護士と会ってから話します」と伝え、黙秘権を行使しましょう。これは、あなたの権利を守るだけでなく、冷静さを取り戻し、記憶を整理するための時間を確保するという意味でも重要です。
黙秘権の上手な使い方と「供述調書」への対応
黙秘権を効果的に使うためには、いくつかのポイントと注意点があります。
- 意思を明確に伝える
ただ黙っているだけでは、捜査官は質問を続けます。「私は黙秘権を行使します」とはっきりと意思表示することが重要です。 - 供述調書への署名・押印は絶対にしない
黙秘権と並んで重要なのが「署名押印拒否権」です。取り調べの最後に、警察官は供述調書を提示し、内容を確認した上で署名と押印(指印)を求めてきます。たとえ黙秘を貫いたとしても、「被疑者は終始黙秘していた」といった内容の調書が作成されることがあります。どのような内容であれ、一度サインをしてしまうと、その内容に同意したと見なされ、後から覆すことはほぼ不可能です。内容に少しでも納得できない点があれば、決して署名・押印をしてはいけません。これは黙秘権とセットで押さえておくべきポイントです。 - 黙秘権のデメリットという誤解
捜査官は「黙っていると反省していないと思われ、裁判官の心証が悪くなるぞ」と言ってくるかもしれません。しかし、これは被疑者を揺さぶるための常套句です。黙秘権の行使が、それ自体で不利益な量刑判断につながることはありません。ただし、全面的に罪を認め、深く反省している事件であれば、正直に供述し、反省の態度を示すことが、結果的に早期の身柄解放や軽い処分につながることもあります。だからこそ、弁護士との相談が不可欠なのです。
弁護士に相談するメリット
黙秘権を適切かつ効果的に行使するためには、弁護士のサポートが欠かせません。
- 黙秘権を使うべきかの的確な判断
ご本人から詳しく話を聞き、事件の見通しを立てた上で、完全黙秘、一部黙秘、あるいは正直に話すなど、あなたにとって最も有利な供述方針をアドバイスします。 - 黙秘権行使のバックアップ
弁護士が「私が接見するまで、一切話す必要はありません」と本人に伝え、捜査機関にもその旨を申し入れることで、不当な取り調べを効果的に牽制します。弁護士の存在が、ご本人が安心して黙秘権を行使するための支えとなります。 - 供述調書の徹底的なチェック
接見の際に、ご本人がサインを求められている供述調書の内容を、法的な観点から厳しくチェックします。少しでも不利な記述や事実に反する部分があれば、署名を拒否するよう助言します。 - 黙秘以外の防御活動の推進
ご本人が黙秘権を行使して時間を稼いでいる間に、弁護士は被害者との示談交渉を進めたり、アリバイ証拠を収集したりと、水面下で様々な防御活動を展開し、早期解決を目指します。
まとめ
黙秘権は、不当な捜査からあなたの身を守り、えん罪を防止するために憲法が保障した、きわめて強力な権利です。特に、無実を主張する事件や、事実関係に争いがある事件では、この権利を最大限に活用すべきです。
しかし、その行使は時として諸刃の剣にもなり得ます。事件の性質を見極めず、ただ黙秘を続けることが最善策とは限らないケースもあります。重要なのは、事件の状況に応じた戦略的な権利の行使です。
そして、その戦略を立てるためには、刑事弁護に関する知識と経験を持つ弁護士のサポートが有益です。取り調べが本格化する前に、一刻も早く弁護士に相談し、万全の態勢で臨むこと。それが、あなたの未来を守るための一手です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、逮捕直後からの迅速な対応で、あなたの大切な権利を守ります。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に
勾留とは?逮捕との違いと勾留を回避するための3つのポイント
はじめに
ご家族が逮捕された後、「勾留(こうりゅう)」という言葉を耳にすることがあります。逮捕だけでも大変なことですが、この「勾留」が決定されると、身体拘束はさらに長期化し、ご本人の社会生活に計り知れない影響を及ぼす可能性があります。失職や退学、周囲からの信用の失墜など、その代償は大きなものになりかねません。
しかし、「逮捕」と「勾留」の違いを正確に理解されている方は多くありません。実は、この2つは異なる手続きであり、勾留を阻止するためには、逮捕後の限られた時間の中で行うべき重要なポイントが存在します。
この記事では、刑事事件における「勾留」とは具体的にどのような手続きなのか、逮捕とは何が違うのかを明らかにし、長期の身体拘束という事態を回避するための「3つの重要ポイント」について解説します。
Q&A
Q1. 勾留されると、どのくらいの期間、家に帰れないのですか?
勾留が決定されると、まず原則10日間、身柄を拘束されます。さらに、検察官が「やむを得ない事由がある」と判断して請求し、裁判官がそれを認めると、さらに最大10日間延長される可能性があります。つまり、逮捕後の最大72時間と合わせると、起訴・不起訴の判断が下されるまでに最長で23日間も警察の留置場などで生活しなければならないことになります。この期間、当然ながら自宅に帰ることも、会社や学校に行くこともできません。
Q2. 勾留中は、家族と面会したり、手紙のやり取りをしたりできますか?
勾留中は、原則としてご家族も面会(接見)が可能です。ただし、1日に1組、時間は15分程度、警察官の立ち会いのもとで行われるなど、厳しい制限があります。また、事件の内容によっては、裁判官の判断で家族との面会や手紙のやり取りすら禁止される「接見禁止」という処分が下されることもあります。この場合、外部と連絡を取る方法は、弁護士との接見に限られてしまいます。
Q3. 勾留されずに済むケースもあるのですか?
はい。逮捕されたからといって、必ず勾留されるわけではありません。検察官が勾留請求をしない場合や、請求しても裁判官が「勾留の必要なし」と判断して却下した場合には、身柄は釈放されます。逮捕後72時間以内に、弁護士を通じて早期に示談を成立させたり、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを説得的に主張したりすることで、勾留を回避できる可能性はあります。
解説
それでは、「勾留」について、より深く掘り下げていきましょう。逮捕との違いを明確に理解することが、勾留回避への第一歩です。
1 勾留とは何か?- 10日間+10日間の長期身体拘束
勾留とは、逮捕に引き続き、被疑者(または起訴後の被告人)の身柄を拘束する、裁判官の許可(勾留決定)によって行われる強制処分です。
その目的は、逮捕と同じく、被疑者が逃亡したり、証拠(証人や物証など)を隠滅したりするのを防ぐことにあります。しかし、その期間は逮捕とは比べ物にならないほど長くなります。
- 勾留期間
原則10日間 - 勾留延長
やむを得ない事由がある場合、さらに最大10日間の延長が可能
つまり、捜査段階における勾留は、合計で最大20日間に及ぶ可能性があるのです。逮捕からの72時間(3日間)と合わせると、起訴されるかどうかが決まるまでに、最長で23日間も社会から隔離されてしまうことになります。
この20日間以上の身体拘束は、ご本人にとって計り知れない不利益をもたらします。
- 会社を無断で長期間欠勤することになり、解雇されるリスクが高まる。
- 学校の授業や試験に出席できず、留年や退学につながる可能性がある。
- 家族や友人との関係が悪化する。
- 事件が職場や近所に知れ渡り、社会的な信用を失う。
このように、勾留は被疑者の人生を大きく変えてしまうほどの深刻な影響力を持っています。
2「逮捕」と「勾留」の決定的違い
目的は似ていますが、「逮捕」と「勾留」は、その主体と期間において決定的な違いがあります。この違いを理解することが重要です。
| 逮捕 | 勾留 | |
| 決定主体 | 主に捜査機関(警察官・検察官) | 裁判官(司法) |
| 期間 | 最大72時間(3日間) | 最大20日間(10日+10日) |
| 法的根拠 | 警察段階(48時間)+検察段階(24時間) | 検察官の請求に基づく裁判官の許可 |
逮捕は、捜査の初期段階で行われる、比較的短期間の身柄拘束です。あくまで捜査機関の主導で行われます(逮捕状は裁判官が発付します)。
一方、勾留は、捜査機関(検察官)からの請求を受けて、中立な立場である裁判官がその必要性を審査し、許可して初めて行われる、より重い処分です。これは、不当な身体拘却から国民の自由を守るという、憲法の理念に基づいています。
つまり、逮捕から勾留へと移行するかどうかは、裁判官の判断にかかっているのです。この「裁判官の判断」に働きかけることこそが、弁護活動の鍵となります。
3 勾留が決まるまでの流れ
勾留はどのようにして決まるのでしょうか。逮捕後の流れを追いながら見てみましょう。
逮捕・送致(~72時間)
逮捕後、警察は48時間以内に被疑者を取り調べ、事件を検察官に送致します。送致を受けた検察官は、24時間以内に自らも取り調べを行います。
検察官による勾留請求
検察官は、逮捕から72時間以内に、「このまま身柄を拘束して捜査を続ける必要がある」と判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行います。
裁判官による勾留質問
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を裁判所に呼び、直接話を聞く機会を設けます。これを「勾留質問(こうりゅうしつもん)」といいます。裁判官は、被疑者に対し、疑われている罪について間違いがないか、何か言い分はないかなどを尋ねます。これは、被疑者が自らの意見を裁判官に伝えられる、きわめて重要な機会です。しかし、実際には一人あたり数分から十数分程度で終わることがほとんどです。
勾留決定 または 勾留請求却下
勾留質問や検察官から提出された証拠などを踏まえ、裁判官が最終的に勾留するかどうかを判断します。
- 勾留決定
裁判官が「勾留の理由と必要がある」と判断した場合、勾留状が発付され、10日間の勾留が始まります。 - 勾留請求却下
裁判官が「勾留の理由または必要がない」と判断した場合、請求は却下され、被疑者は直ちに釈放されます。
この流れの中で、いかにして裁判官に「勾留の必要はない」と判断させるかが、勝負の分かれ目となるのです。
【最重要】勾留を回避するための3つのポイント
では、具体的に何をすれば勾留を回避できるのでしょうか。弁護士が実務上、最も重視している3つのポイントを解説します。
ポイント1:逮捕後72時間以内に弁護士に依頼する
何よりもまず、スピードが命です。勾留が決定されてしまってからでは、その決定を覆すのは容易ではありません。勾留を阻止するためには、検察官が勾留請求をする前、あるいは裁判官が勾留決定を下す前の逮捕後72時間以内に弁護士が活動を開始する必要があります。
弁護士は、検察官や裁判官に対し、勾留すべきでない理由を法的な観点からまとめた意見書を提出します。また、勾留質問の前にご本人と接見し、「裁判官に何を、どのように伝えれば効果的か」を具体的にアドバイスします。たった一人で勾留質問に臨むのと、弁護士と綿密な打ち合わせをして臨むのとでは、結果が大きく変わる可能性があります。
ポイント2:被害者がいる事件では、迅速に示談を進める
窃盗、傷害、暴行、痴漢といった被害者が存在する犯罪の場合、被害者との示談交渉を迅速に進めることが、勾留回避に絶大な効果を発揮します。
示談が成立し、被害者から「加害者を許す」という宥恕(ゆうじょ)文言の入った示談書や、「被害届を取り下げる」という内容の嘆願書などを得ることができれば、それは「当事者間で事件が解決に向かっている」ことを示す強力な証拠となります。
これにより、裁判官は以下のように判断する可能性が高まります。
- 「被害者に接触して証拠隠滅(脅迫など)を図る恐れは低い」
- 「すでに当事者間で解決しており、身柄を拘束してまで厳罰を科す必要性は低い」
結果として、勾留請求が却下される可能性が高まります。しかし、加害者側が直接被害者と接触するのは困難であり、かえって事態を悪化させる危険もあります。示談交渉は、冷静かつ専門的な交渉が可能な弁護士に任せることが望ましいといえます。
ポイント3:「逃亡・証拠隠滅の恐れがない」ことを具体的に主張する
勾留が認められるのは、法律上、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、かつ、以下のいずれかに該当する場合です。
- 定まった住居を有しないとき。
- 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
言い換えれば、これらの要件に当てはまらないことを説得的に主張できれば、勾留は回避できます。弁護士は、ご本人やご家族から事情を聞き取り、以下のような客観的な証拠を集めて、裁判官に「逃亡や証拠隠滅の恐れはない」と主張します。
逃亡の恐れがないことの証拠
- 安定した職についていること(在職証明書、給与明細など)
- 家族が身元引受人となり、監督を誓約していること(身元引受書)
- 持ち家や賃貸アパートなど、定まった住居があること(登記簿謄本、賃貸借契約書など)
- 病気の治療など、定期的に通院の必要があること(診断書など)
証拠隠滅の恐れがないことの証拠
- 事件に関する重要な証拠(凶器、防犯カメラ映像など)がすでに警察に押収されていること
- 共犯者がおらず、口裏合わせの心配がないこと
- 被害者との示談が成立し、これ以上接触する必要がないこと
- 深く反省し、捜査に協力する意思を示していること
これらの材料を、ただ口頭で伝えるだけでなく、弁護士が法的に意味のある「意見書」としてまとめ、証拠と共に提出することで、裁判官を説得する力が増します。
弁護士に相談するメリット
勾留を回避するために弁護士ができることは、ここまで解説してきたポイントに集約されます。改めて、そのメリットを整理します。
- 勾留決定前の迅速な対応
検察官や裁判官に対し、勾留の必要性がないことを示す意見書を迅速に提出。勾留質問に向けた的確なアドバイスで、ご本人をサポートします。 - 専門家による示談交渉
ご本人やご家族に代わり、被害者と冷静かつ円滑に示談交渉を進めます。早期の示談成立は、勾留回避の最も有効な手段の一つです。 - 勾留決定後の不服申し立て
万が一勾留が決定されてしまっても、諦める必要はありません。弁護士は「準抗告」という不服申し立ての手続きを行い、勾留決定の取り消しを求め、最後まで身柄解放を目指して戦います。 - 接見禁止への唯一の対抗策
もし「接見禁止」がついてしまい、家族との面会もできなくなった場合、弁護士との接見が唯一、外部と連絡を取り、詳細な打ち合わせをする手段となります。ご本人の精神的孤立を防ぎ、防御活動を続ける上で、その役割は重要となります。
まとめ
「逮捕」は最大72時間の短期決戦ですが、「勾留」は最大20日間にも及ぶ長期戦の始まりです。勾留されてしまうかどうかは、その後の人生を左右する、まさに運命の分岐点と言えます。
その分岐点において、良い結果を導き出すための鍵は、以下の3つです。
- 逮捕後72時間以内という時間制限の中で、迅速に弁護士に相談・依頼すること。
- 被害者がいる場合は、弁護士を通じて一日も早く示談を成立させること。
- 弁護士のサポートのもと、「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」ことを客観的な証拠で示すこと。
もしご家族が逮捕され、「勾留されるかもしれない」という不安の中にいるのであれば、どうか一刻も早く行動を起こしてください。時間が経てば経つほど、打てる手は少なくなっていきます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件に関する豊富な経験に基づき、勾留阻止・早期の身柄解放に向けた弁護活動に全力を尽くします。ご相談者様の不安に寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。まずは、お電話でご相談ください。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に
逮捕されたらどうなる?逮捕から起訴までの72時間の流れを徹底解説
はじめに
「家族が警察に逮捕された」
ある日突然、こんな連絡を受けたら、誰でも冷静ではいられないでしょう。頭が真っ白になり、何が起きているのか、これからどうなるのか、不安でいっぱいになるはずです。
実は、逮捕されてから最初の72時間は、その後の人生を大きく左右する、きわめて重要な期間です。この期間にどのような対応をとるかによって、身柄拘束が長引くか、早期に釈放されるか、さらには前科がつくかどうかの分かれ道になることも少なくありません。
この記事では、逮捕されてから検察官が勾留を請求するまでの「72時間」に焦点を当て、その具体的な流れ、行われる手続き、そしてご本人やご家族が取るべき対処法について解説します。
Q&A
Q1. 逮捕されたら、すぐに家族に連絡できますか?
いいえ、逮捕直後にご本人が自ら家族に電話などで連絡することは、原則としてできません。逮捕されると、携帯電話などの私物は取り上げられてしまいます。警察官が家族に逮捕の事実を連絡することはありますが、必ず連絡してくれるとは限りません。また、連絡があったとしても、事件の内容について詳しく教えてもらえることは期待できません。ご本人の状況を正確に把握し、外部と連絡を取るためには、弁護士による接見(面会)となります。
Q2. 逮捕から勾留請求までの間、家族は面会できますか?
逮捕後、検察官による勾留請求までの最大72時間は、たとえご家族であっても面会(接見)が認められないケースが大半です。これは、捜査の初期段階において、口裏合わせなどの証拠隠滅を防ぐためです。しかし、弁護士であれば、この期間中も警察官の立ち会いなく、いつでもご本人と面会し、法的なアドバイスを送ることができます。この「弁護士接見権」は、逮捕された方にとって非常に重要な権利です。
Q3. 逮捕されたら、必ず前科がついてしまいますか?
いいえ、「逮捕=前科」ではありません。前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した場合につくものです。逮捕は、あくまで捜査の第一段階に過ぎません。逮捕された後でも、検察官が「起訴しない」という判断(不起訴処分)を下せば、刑事裁判は開かれず、前科がつくことはありません。逮捕後の早い段階から弁護士が介入し、被害者との示談交渉や検察官への働きかけを行うことで、不起訴処分を獲得し、前科を回避できる可能性は十分にあります。
解説
それでは、逮捕後の72時間に何が起こるのか、時系列に沿って詳しく見ていきましょう。この流れは刑事訴訟法という法律で厳格に定められています。
1 逮捕(〜0時間):身柄拘束の始まり
「逮捕」とは、犯罪の疑いがある人(被疑者)の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、強制的に身柄を拘束する手続きのことです。逮捕には、大きく分けて3つの種類があります。
- 通常逮捕
裁判官が事前に発付した逮捕状に基づいて行われる、最も一般的な逮捕です。警察が事前に捜査を進め、容疑が固まった段階で逮捕に踏み切ります。 - 現行犯逮捕
痴漢や万引きなど、目の前で犯罪が行われている最中や、犯行直後に逮捕する場合です。この場合、逮捕状は必要なく、警察官だけでなく一般人でも逮捕することができます。 - 緊急逮捕
殺人罪などの重大犯罪で、嫌疑が十分にあるものの、逮捕状を請求する時間的余裕がない場合に、令状なしで行われる逮捕です。ただし、逮捕後には直ちに裁判官に逮捕状を請求する手続きが必要です。
いずれのケースでも、逮捕されると警察署に連行され、留置場(または拘置所)で身体を拘束されることになります。この時点から、時間との闘いが始まります。
2 警察官による取り調べと送致(逮捕後〜48時間以内)
逮捕後、警察は48時間以内に、被疑者の取り調べを行い、事件に関する書類や証拠物とともに、事件を検察官に引き継がなければなりません。この手続きを「送致(そうち)」または「送検(そうけん)」と呼びます。
この48時間の間、警察署の取調室で、警察官による集中的な取り調べが行われます。
取り調べで作成される「供述調書」の重要性
取り調べでは、事件について詳細な事情聴取が行われ、その内容は「供述調書(きょうじゅつちょうしょ)」という書面にまとめられます。この供述調書は、後の検察官の判断や、起訴された場合の刑事裁判において、きわめて重要な証拠となります。
注意しなければならないのは、一度署名・押印してしまった供述調書の内容を、後から覆すことは非常に困難であるという点です。警察官に言われるがままに、事実に反する内容や、自分にとって不利な内容の調書にサインしてしまうと、それが証拠となり、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。
黙秘権と署名押印拒否権
被疑者には、憲法で保障された重要な権利があります。
- 黙秘権
言いたくないこと、自分に不利益なことは、一切話す必要はありません。 - 署名押印拒否権
作成された供述調書の内容に納得がいかない場合は、署名や押印を拒否することができます。
しかし、逮捕され、閉鎖的な空間で連日取り調べを受けるという極度のプレッシャーの中で、これらの権利を適切に行使することは容易ではありません。警察官から「正直に話せば早く帰れる」「黙っていると不利になるぞ」といった誘導を受けることも考えられます。このような状況で、たった一人で捜査官と対峙するのは、精神的に大きな負担となります。
3 検察官による取り調べと勾留請求(送致後〜24時間以内)
警察から事件の送致を受けた検察官は、自らも被疑者を取り調べます。そして、送致を受けてから24時間以内(つまり、逮捕から合計して72時間以内)に、次のいずれかの判断を下さなければなりません。
- ① 裁判官に勾留(こうりゅう)を請求する
- ② 被疑者を釈放する
勾留請求とは?
検察官が「被疑者の身柄を引き続き拘束して捜査する必要がある」と判断した場合、裁判官に対して「勾留請求」を行います。勾留が認められると、原則として10日間、さらに捜査が必要な場合には最大10日間延長され、合計で最大20日間も身柄拘束が続くことになります。
勾留が認められる主な要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことに加え、以下のいずれかに該当する場合です。
・定まった住居がない
・証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
・逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
72時間が経過する前に行われるこの勾留請求が、身体拘束が長期化するかどうかの最初の大きな関門となります。
釈放されるケース
一方で、検察官が「身柄拘束の必要はない」と判断した場合には、被疑者は釈放されます。例えば、以下のようなケースです。
・嫌疑が不十分である
・容疑が晴れた
・罪が軽微であり、逃亡や証拠隠滅の恐れがない
ただし、この時点での釈放は、必ずしも「不起訴処分」が確定したわけではありません。身柄は解放されますが、捜査は継続される「在宅事件」として扱われる場合がほとんどです。
以上が、逮捕から72時間の流れです。この期間は、外部との連絡が遮断された中で、今後の刑事手続きの方向性を決定づける重要な捜査が行われます。だからこそ、この72時間にいかに迅速かつ適切な対応ができるかが、その後の運命を大きく左右するのです。
弁護士に相談するメリット
逮捕後の72時間という限られた時間の中で、ご本人やご家族だけでできることには限界があります。この危機的な状況を乗り越えるために、弁護士のサポートは重要です。早期に弁護士に相談・依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。
ただちに本人と接見(面会)し、精神的な支えとなる
前述の通り、逮捕後の72時間は家族ですら面会することは困難です。しかし、弁護士は「接見交通権」という権利に基づき、逮捕直後から、いつでも、誰の立ち会いもなくご本人と面会することができます。
突然逮捕され、孤独と不安の中にいるご本人にとって、弁護士の存在は大きな精神的な支えとなります。事件の見通しや今後の流れを伝えることで、ご本人を落ち着かせ、冷静な判断ができるようにサポートします。
取り調べに対する具体的なアドバイスで、不利な供述を防ぐ
弁護士は、捜査のプロである警察官や検察官と対等に渡り合うための、法的な知識と経験を持っています。接見を通じて、ご本人から詳しく話を聞き、以下の点について具体的なアドバイスを行います。
・黙秘権をどのような場面で、どのように使うべきか
・供述調書に署名・押印する前に、必ず確認すべきポイント
・事実と異なる内容の調書が作成された場合の対処法
・捜査官からの不当な誘導や圧力への対抗策
これらのアドバイスにより、意図せずして自分に不利な供述調書が作成されるリスクを大幅に減らすことができます。
早期の身柄解放(釈放)に向けた活動
弁護士の最も重要な役割の一つが、勾留を防ぎ、早期の身柄解放を実現することです。検察官が勾留請求をする前、あるいは裁判官が勾留を決定する前に、弁護士は以下のような活動を行います。
- 検察官への意見書提出
逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、家族の監督が期待できることなどを具体的に主張し、勾留請求をしないよう検察官に働きかけます。 - 裁判官との面談
勾留請求が行われた場合、裁判官と面談し、勾留の必要性がないことを直接訴え、勾留請求を却下するよう求めます。 - 準抗告(じゅんこうこく)
万が一、勾留が決定されてしまった場合でも、その決定に対して不服を申し立てる(準抗告)ことで、身柄解放を目指します。
弁護士が迅速に動くことで、勾留という長期の身柄拘束を回避できる可能性が高まります。
被害者がいる事件での迅速な示談交渉
痴漢、暴行、窃盗など、被害者が存在する事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが、その後の処分を大きく左右します。特に逮捕直後の段階で示談が成立すれば、検察官が「当事者間で解決済み」と判断し、勾留請求をせずに釈放したり、最終的に不起訴処分としたりする可能性が格段に上がります。
しかし、加害者本人やその家族が直接被害者と交渉しようとしても、連絡先を教えてもらえなかったり、感情的な対立から交渉が難航したりするケースが多いと言えます。弁護士が代理人として間に入ることで、被害者の感情にも配慮しつつ、冷静かつ円滑に示談交渉を進めることが可能になります。
まとめ
この記事で解説したように、逮捕後の72時間は、法律で定められた手続きが分刻み、時間刻みで進んでいく、非常にタイトで重要な期間です。
- 逮捕後48時間以内
警察による取り調べと検察官への送致 - 送致後24時間以内
検察官による取り調べと勾留請求の判断
この短い時間の中で、ご本人は外部から遮断された状態で厳しい取り調べを受け、今後の人生を左右するかもしれない「供述調書」が作成されます。この危機的状況を乗り切るためには、法律の専門家である弁護士の、迅速かつ的確なサポートが絶対に必要です。
もし、あなたやあなたの大切なご家族が逮捕されてしまったなら、どうか一人で悩まず、一刻も早く弁護士にご相談ください。「まだ逮捕されたばかりだから」「もう少し様子を見てから」と考えている時間が、取り返しのつかない結果につながることもあります。
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が、ご依頼者様の不安に寄り添い、権利を守るためにサポートいたします。初回の相談は無料です。まずはお電話いただき、現状をお聞かせください。早期の対応が、最善の解決への第一歩です。
その他の刑事事件コラムはこちら
初回無料|お問い合わせはお気軽に